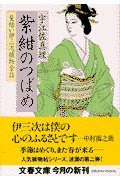2024年7月26日
午後はのんびりと読書
2024年7月22日
またまたつらつらと雑談などなど
2024年7月21日
【読了】草枕
明治期の文学者、夏目漱石の初期の中編小説。初出は「新小説」[1906(明治39)年]。「智(ち)に働けば角(かど)が立つ。情に棹(さお)させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」との書き出しは有名。三十歳の画家の主人公が文明を嫌って東京から山中の温泉宿(熊本小天温泉)を訪れ、その宿の美しい娘、那美と出会う。那美の画を描くことをめぐって展開するストーリーに沿って、俗塵を離れた心持ちになれる詩こそ真の芸術だという文学観と「非人情」の美学が展開される。低徊趣味や俳句趣味の色濃い作品。(アマゾンHPより)
「吾輩は猫である」「坊っちゃん」に続く、夏目漱石の初期の作品。
物語性のあるお話というよりは、漱石の芸術観、人生観みたいなものを画工(えかき)である主人公に語らせた小説とも随筆とも言い難い、でもただひたすらに文章が美しい、不思議な作品でした。
正岡子規も認めるほどに俳句や漢詩の才能にも溢れていた夏目漱石の文章は、どこかリズム感が感じられ、息継ぎも自然にできるような呼吸感のある、旋律性をもった文章だなといつも読みながら感じます。
以下、解説に掲載されていた漱石の言葉。
「『草枕』は、この世間普通にいう小説とはまったく反対の意味で書いたのである。ただ一種の感じ――美しい感じが読者の頭に残りさえすればよい。……さればこそ、プロットもなければ、事件の発展もない」
漱石の狙いどおり、美しさがとても頭に残る、絵画のようでもあり音楽のようでもある素敵な作品でした。
私が読んだのは祖父の文学全集の本でしたが、注釈や解説がとても詳しくいろいろ勉強になりました。昔の本なので字など読みにくいですがだんだん慣れてきました。昔っぽいフォントを読み続けていたり紙をめくったりしていると昭和にトリップした感じになれます(笑)。
2024年7月20日
不思議なくらい、暑いけど暑くない・・・そして夏バテ対策
2024年7月19日
【読了】漱石の思い出
NHKのドラマ「夏目漱石の妻」で存在を知ったこの本をようやく読み終えました。
名作「坊ちゃん」に描かれる松山でのいろいろな出来事、夏目家の親戚のこと、熊本での婚礼の様子から微に入り細を穿って語られる文豪・夏目漱石の日常生活。お見合いで出会ってから死別するまでを共に過した鏡子夫人なければ、垣間見ることのできなかった人間・漱石の赤裸々な姿を浮き彫りにする。鏡子が漱石と生活を共にした二十年間、一日も欠かさず漱石が狂気の沙汰を演じたわけではない。周期的に訪れた狂気の時のほうが遥かに短いのである。しかも自分は小説家だから、常軌を逸しても許されるのだとか、ものを書けないイライラを家族にぶつけてもよいのだという傲慢さや身勝手さを、漱石という人は微塵も有していない。(解説・半藤未利子より)(アマゾンHPより)
460ページもあるなかなか分厚い本でしたが、思った以上におもしろくて結構あっという間に読み終えることができました。
上の半藤未利子さん(夏目漱石のお孫さんでジャーナリストで作家の半藤一利さんの奥様)の解説のとおり、夏目漱石は神経衰弱の病からくる妄想癖や癇癪、暴力がなければおおらかであまり小さなことを気にしたりしない、それどころかユーモアがあって心あたたかい楽しい人だったのだなぁというのが読んでいてよく分かりました。とにかく漱石のもとに集まってくる人の数が半端ないのも印象的でした。
それでも怖かったときは想像を絶する怖さだったらしく、とくに上の2人のお子さんは漱石の神経衰弱がとても酷かったころにまだ小さかったため、優しい漱石のほうが圧倒的に多かったのにそのころの怖い漱石像が骨身にまでしみていて最後まで慣れ親しむことができなかったそうです。
「いろんな男の人をみてきたけど、あたしゃお父様が一番いいねぇ」
結局のところ、奥様である夏目鏡子さんがこの本(実際はインタビュー形式だったものを娘婿である松岡譲さんがまとめたもの)で一番伝えたかったことは、このひと言だったんだろうなと思いました。
ちなみにこの本を出そうと思ったきっかけは、ラフカディオ・ハーンの奥様である小泉セツさん(NHKの朝ドラ化が決まったそう!)がハーンの思い出を記されたこと(おそらく先日読んだ「日本の面影II」に収録されている「思い出の記」)だったそう。
漱石はハーンの後に教鞭を執ってほしいと頼まれたのを「自分には無理だ」と一度は断っています。
同年代に生きた2人の全く別々の人物やその家族の様子も窺えたり比較できたりして、なかなか興味深いつながりを感じました。
結構前から夏目漱石の「草枕」をちょこちょこと読んでいて、こちらも明日中には読み終えそうです。
「すみれの花はいいなあ」な生き方
たまたま読んだWeb記事に私の好きな数学者、岡潔について書いてあったのですが、岡潔の言っていた「すみれの花はいいなあ」な生き方をしていきたいなと、つくづく思いました。
岡潔は、すみれの花を見て「あれはすみれの花だ」「むらさき色だ」と理性的に見るのに対し「すみれの花はいいなあ」と感じることが情緒であり、教育にはこの「情緒」が必要だと言っています。
そんなに難しいことではなく、ただ自分の感じる「いいなあ」に素直であり続ければ情緒は育まれていくものだと思うのですが、お金を稼ぐことだったり出世だったり、人と比べて自分はまだまだだから頑張らなきゃだったり、いろいろな思いによって「素直になる」のがなかなかできないのが今の社会なのかなと思います。そんな悠長なことを感じている場合じゃないと思う人もいるのかもしれません…。
いや、、、もしかしたらその「いいなあ」にすら気づかないぐらい疲弊している人が多いのかも、とも思います。
いつだったか、有名大企業でバリバリ働く友人が「幸せってなんだろうね」と言うんですね。
私は、「私は毎日普通に暮らしているのが幸せに思う」と言いました。今思えばこれはちょっと言葉足らずだったなあ…。でも私が言わんとしていたことは、「すみれの花はいいなあ」ということなんです。
出勤の仕事の帰り、あぁ疲れたなぁと思いながらとぼとぼ歩いていると、時折すーっと心地よい夜風が吹くことがあります。そんなとき、ふっと「ああ気持ちいいなぁ」と思ってぱっと顔を上げると、うちの目の前にある並木の葉が風にゆさゆさと揺れていてとっても癒やされます。ゆさゆさといっている音も「ああいいなあ」と思います。
そんなときは縮こまっていた胸もぱーっと開いていく感じがします。結局「幸せ」ってそんなのの積み重ねなんじゃないかなというのが、今の私の実感です。
私が思うに、もちろん例えば「ダビンチの絵はいいなぁ」とか「モーツァルトはいいなぁ」とかでもいいのですが、やっぱり「自然」は特に情緒の形成に重要な役割を果たしているもので、だからこそ「すみれの花はいいなあ」が大事だと思うのです。
友人は「なんか今すごくいい話を聞いた気がする」と言っていましたが、どう受け取ったのかはわかりません。
でも、何かを「いいなあ」と感じることすらできないくらい、働きすぎて疲れすぎているんだなと思って、なんだか心がきゅーっと苦しくなったのを覚えています。
今日ちょっと別の人からこの友人と同じような話を聞いて、この友人の話や「すみれの花はいいなあ」を思い出しました。
私は「すみれの花はいいなあ」な生き方がこれからもしていきたいなぁとしみじみ思った1日でした。
2024年7月15日
練習中の曲
2024年7月14日
母との想い出
2024年7月13日
久々にベレ出版のHPを見たら欲しい本がいっぱい
2024年7月11日
繁忙期のようです
2024年7月9日
中年の危機
明日〆切の書籍の校正の仕事が終わってちょっとほっと一息です。
明日原稿を持っていくのですが、その後少し他の仕事をして帰らねばならなくなりちょっぴり憂鬱。仕事をいただけるのはすごくありがたくて、できればもっと校正スキルを向上させたいからどんどん仕事をしていきたいのですが、いかんせん疲れやすい身体が年齢的なものもあってさらに疲れやすくなりすぐめげてしまう。。。
明日は夕方から雨が降るみたいだし18時ぐらいは電車が一番混む時間帯なので、帰りは遅めになりそう。
6月半ばからずっと休みなく仕事をしている感じで心があまり安まらず、ちょっと疲れています。。。鬱までいかなくてもちょっぴり無気力気味です。
周りの同年代の人たちの話を聞くとどうも多くがそんな感じで、自分も含めていわゆる「中年の危機」に陥っているなぁと実感しています😥
「中年の危機」とは、"中年期を迎えた個人が経験するアイデンティティや自己肯定感の変化、すなわち中年期の心理的危機"だとか。(Wikipediaより)
私は自分で中年の危機に入ったなぁというのが自覚できるし、フリーランスだからたとえ稼ぎが減ったとしても身体を労るためだ、仕方ない…と思って休めるのですが、普通に働いている方々はそもそも忙しすぎたり日々のストレスでいっぱいいっぱいで、そのことを自覚する余裕が持てるのだろうか、自覚して休もうと思えるのだろうか…と思ってしまいます。
もちろん休めるなら休みたいよと思って無理して働いているのだと思うけれど、だんだん麻痺してくるのかな。または、中年の危機にさしかかると自分のことを振り返ったりこれからの将来のことを一度立ち止まって考えたりするようになるようですが、それが辛い人もいるだろうと思うので、できるだけ考えないように自分を意識的にか無意識的にか忙しくしている、というのもあるのかもしれません。
私のようにしばらく出勤して、そして家で、などと働き方がいろいろだとそれはそれで意外と疲れるのですが、知り合いの話なんかを聞いているともう長年の疲れが蓄積していて、それがこの中年の危機でマックスになってきつつある感じがして、身体を壊さないか心配しています。
何が言いたいのか、、、疲れたぁぁという単なる愚痴です😂
お風呂に入って早めに寝ます~。
2024年7月8日
【東京散歩】お茶の水~東大赤門
先日、お茶の水スタートで↓のお散歩コースを参考にぶらぶらしてきました。
湯島駅からはじめる湯島・本郷散歩
〜東大と天神さまと文人ゆかりの街だから、知的好奇心満開のエリア〜
夕方激しい雨に見舞われて、途中で終了してしまったため、またリベンジしたいと思います。
まずJRか地下鉄丸ノ内線のお茶の水で電車を降りると、すぐに「湯島聖堂」があります。
ちょっと台湾にあるような雰囲気の建物でした(中国に行ったことがないので分かりませんが、中国にあるような建物なのかな)。人が少なくとっても静かで落ち着く場所でした。
前回のお散歩のとき(品川区~港区だったかな?)と違い、文京区は木製の坂の標しがなかったので残念。大体が↓のような説明書きのある看板になっていました。実盛坂の写真を撮り忘れたので、こちらのサイトを見ていただくと高低差が分かると思います。